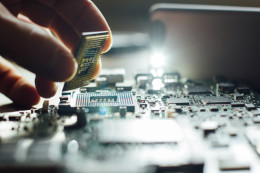ハイテク労働者は米国を目ざす
――インフレ予防に移民が果たす役
2000年8月号

空前の経済ブームに沸くアメリカにとっての唯一の懸念はインフレである。理論的には、労働需要の高まりはインフレを誘発しかねないが、情報通信・ハイテク部門を中心に、インドなどからの技術専門職のアメリカへの移民が急増しており、彼らの存在は、ハイテク部門の成長だけでなく、労働市場の需給バランスを維持する安全弁の役割を果たしている。金利引き上げを回避しつつ、ハイテク部門の成長を維持する鍵を握っているのは、意外にも自由な人の流れなのだ。