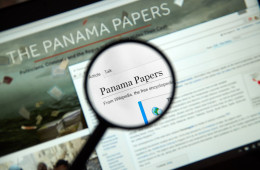人工知能と「雇用なき経済」の時代
―― 人間が働くことの価値を守るには
2016年8月号

さまざまな事例を検証し、相関パターンを突き止め、それを新しい事例に適用することで、コンピュータはさまざまな領域で人間と同じか、人間を超えたパフォーマンスを示すようになった。道路標識を認識し、人間の演説を理解し、クレジット詐欺を見破ることもできる。すでにカスタマーサービスから、医療診断までの「パターンをマッチさせるタスク」は次第に機械が行うようになりつつあり、人工知能の誕生で世界は雇用なき経済へと向かいつつある。今後時給20ドル未満の雇用の83%がオートメーション化されるとみる予測もある。労働市場は大きく変化していく。新しい技術時代の恩恵をうまく摘み取るだけでなく、取り残される人々を保護するための救済策が必要になる。間違った政策をとれば、世界の多くの人を経済的に路頭に迷わせ、機械との闘いに敗れた人を放置することになる。