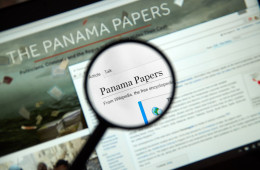貿易叩きという歴史的な間違い
―― なぜ真実が見えなくなって
しまったか
2016年9月号

ドナルド・トランプは、「愚かな」交渉人がまとめたひどい貿易合意のせいで、中国、日本、メキシコがアメリカを貿易面で追い込んでいると訴えている。ヒラリー・クリントンでさえ、反対派に歩調を合わせざるを得なくなり、いまやTPPに反対であると明言している。現実には、貿易はアメリカに大きな利益をもたらしている。雇用喪失の85%以上はオートメーション化による生産性の向上が原因で、貿易が原因による雇用喪失は13%にすぎない。それでも、大統領候補たちは貿易を激しく批判し、それが歴史的な間違いであるにも関わらず、議会によるTPP批准まで危険にさらされている。現実にはアメリカは貿易上の問題には直面していない。問題は、かつて非熟練労働者が中間層の仲間入りを果たすことに道を開いた経済的なはしごが壊れてしまったことだ。