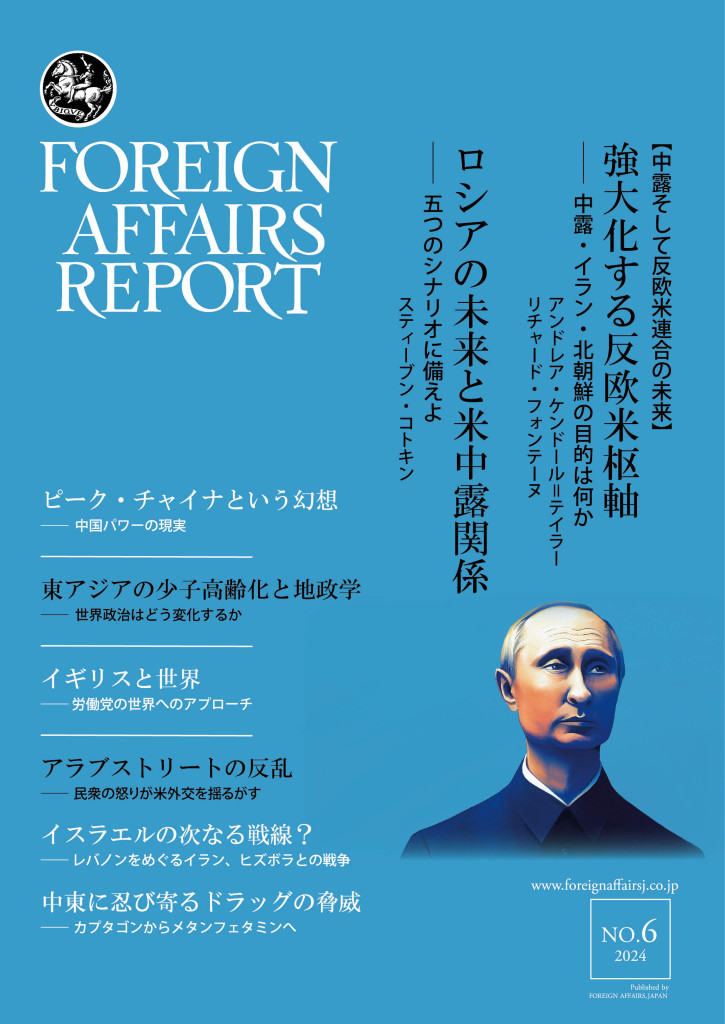
フォーリン・アフェアーズ・リポート2024年6月号 目次
中露そして反欧米連合の未来
-

強大化する反欧米枢軸
中露・イラン・北朝鮮の目的は何か雑誌掲載論文
ウクライナ戦争をきっかけに、中国・ロシア・イラン・北朝鮮は、経済、軍事、政治、技術的な結びつきを強め、共有する利益を特定し、軍事・外交活動を連携させつつある。すでに、地政学状況は変化している。実際、中国の台湾侵攻を前にアメリカが軍事介入を決断すれば、ロシアはヨーロッパの別の国に対して軍事行動を起こし、イランや北朝鮮はそれぞれの地域で脅威をエスカレートさせるかもしれない。たとえ新枢軸が直接的に侵略を連動させなくても、同時多発的な衝突が欧米を圧倒する恐れがある。さらなる連携がもたらす破壊的影響を管理し、中露・北朝鮮・イランの枢軸がグローバル・システムを動揺させないようにすることを、米外交の中核目的に据える必要がある。
-

ロシアの未来と米中露関係
五つのシナリオに備えよ雑誌掲載論文
ロシアと中国は、米主導の国際システムにおける責任ある利害関係者に変貌させられるような相手ではない。彼らの「人格」を作り変えようと努力しても、反感を買い、幻滅するだけだ。むしろ、どのような展開が待ち受けているかに備えるべきだろう。特に、ロシアについてはいくつかのシナリオが考えられる。ロシアは中国に隷属するか、このまま衰退の道を辿るかもしれない。一方、共通点の多いフランスに似た存在になっていくかもしれない。逆に中国を操るようになる可能性も、カオスに陥っていく危険もある。少なくとも、「反ロシアにこり固まった欧米」というプーチンの主張を裏付けるような言動をみせてロシア人をさらにプーチンの下に結集させるのではなく、欧米は「プーチンとロシアを分離したい」と望むロシア人を助けるべきだろう。
-
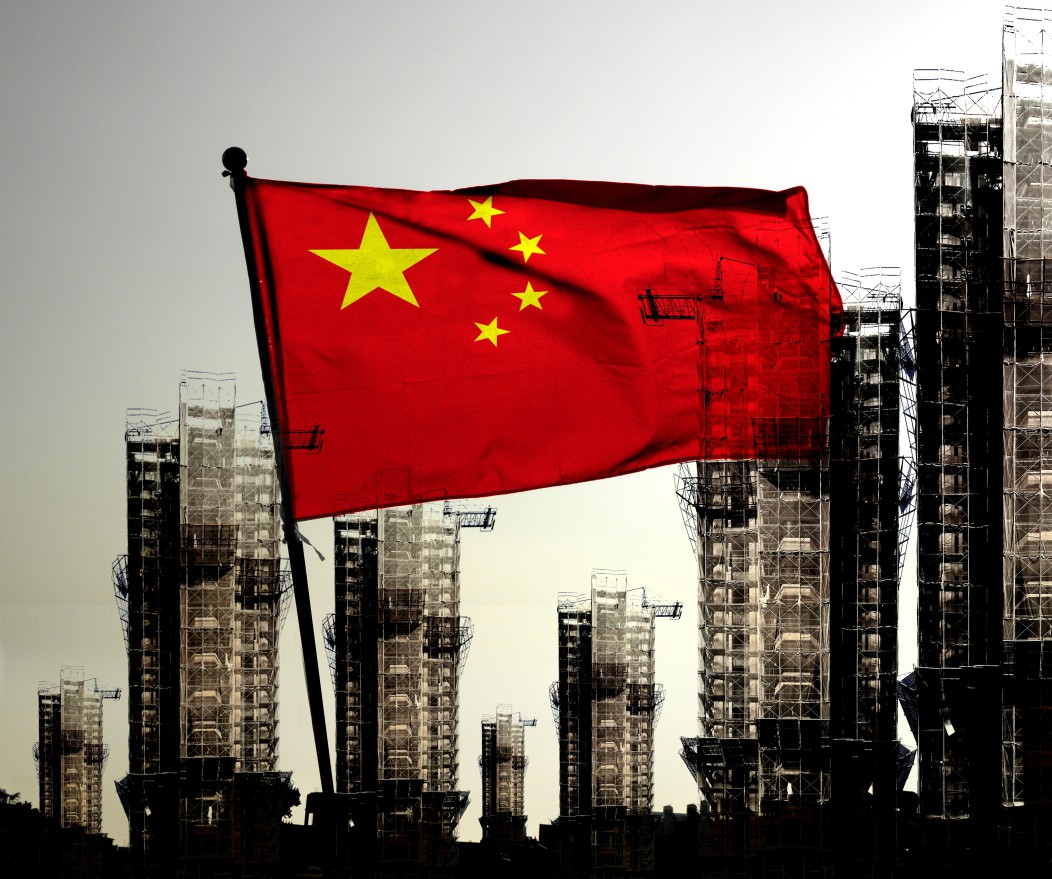
ピーク・チャイナという幻想
中国パワーの現実雑誌掲載論文
経済的に衰退する中国には、もはや「かつてのような力はない」のか。現実には、中国共産党は、大方の予測を覆して、危機をうまく切り抜けることが多く、習近平は現在の経済状況について心配していない。むしろ、現状は、より強く、持続可能な経済になるための成長痛を経験しているようなもので、近代化目標に向かって突き進めるように、経済を再構築するための厳しい選択をしていると北京では考えられている。中国の指導者たちは、自国がピークアウトしたかどうかは心配していない。たとえ成長のペースは鈍化しても、米中間のギャップは縮まり続けていると確信している。
-

機能不全のアメリカ
中露を抑止できるのかSubscribers Only 公開論文
アメリカは、ひどく危険な状況にある。攻撃的な敵対国に直面しつつも、相手を思いとどまらせるのに必要な団結と強さを結集できずにいる。米市民は内向きになり、議会は言い争い、大統領もアメリカの役割について十分な説明をしていない。習近平やプーチンのような指導者をうまく抑止するには、確固としたコミットメントと一貫した対応を示さなければならない。だが現実には、機能不全がアメリカのパワーを不安定で信頼できないものにしている。リスクを冒しやすい独裁者を、潜在的に壊滅的な事態をもたらす、危険な賭けに向かわせようとしている。・・・
-

欧米の偽善とロシアの立場
ユーラシア連合と思想の衝突Subscribers Only 公開論文
冷戦が終わると、欧米の指導者たちは「ロシアは欧米と内政・外交上の目的を共有している」と考えるようになり、何度対立局面に陥っても「ロシアが欧米の影響下にある期間がまだ短いせいだ」と状況を楽観してきた。だが、ウクライナ危機がこの幻想を打ち砕いた。クリミアをロシアに編入することでモスクワは欧米のルールをはっきりと拒絶した、しかし、現状を招き入れたのは欧米の指導者たちだ。北大西洋条約機構(NATO)を東方に拡大しないと約束していながら、欧米はNATOそして欧州連合を東方へと拡大した。ロシアが、欧米の囲い込み戦略に対する対抗策をとるのは時間の問題だった。もはやウクライナを「フィンランド化」する以外、問題を解決する方法はないだろう。ウクライナに中立の立場を認め、親ロシア派の保護に関して国際的な保証を提供しない限り、ウクライナは分裂し、ロシアと欧米は長期的な対立の時代を迎えることになるだろう。
-

中ロ関係の真実
水面下で進む包括的パートナーシップSubscribers Only 公開論文
ウクライナ戦争と欧米の対ロ制裁は、ロシアの経済的・技術的な対中依存をかつてないレベルへ引き上げている。軍事であれ、金融であれ、両国はかなりの協力関係にある。実際、習近平とプーチンが3月の会談で新たな軍事協定について折り合いをつけたと考える理由は十分にある。中国はロシアに対するさまざまな手立てをもっているが、対米関係の軋轢ゆえに、中国にとってロシアは「必要不可欠なジュニアパートナー」でもある。中国に、これほど多くの恩恵をもたらしてくれる友好国もない。地球上もっともパワフルなアメリカとの長期的な対立に備えつつあるだけに、習近平は、あらゆる支援を必要としている。
-

ロシアの反欧米連合
アメリカの敵を束ねるとSubscribers Only 公開論文
ウクライナでの戦争が「ロシアのパワー、利益、影響力を大きく低下させている」と欧米の高官が状況を捉えているのなら、それは考え直す必要があるだろう。ベネズエラから北朝鮮まで、ロシアは、アメリカやヨーロッパを敵視する多くの国々との軍事協力を強化し、深化させている。これらの国々には、欧米という敵を共有している以上の共通点はあまりないかもしれないし、特に強力な国もない。しかし、これらの国々が一緒になれば、モスクワがウクライナとの戦争を続けるのを助けることができる。アメリカはこの「ロシアの枢軸」に対するバランスをとるために、欧米のパートナーシップと同盟に再投資する必要がある。
-
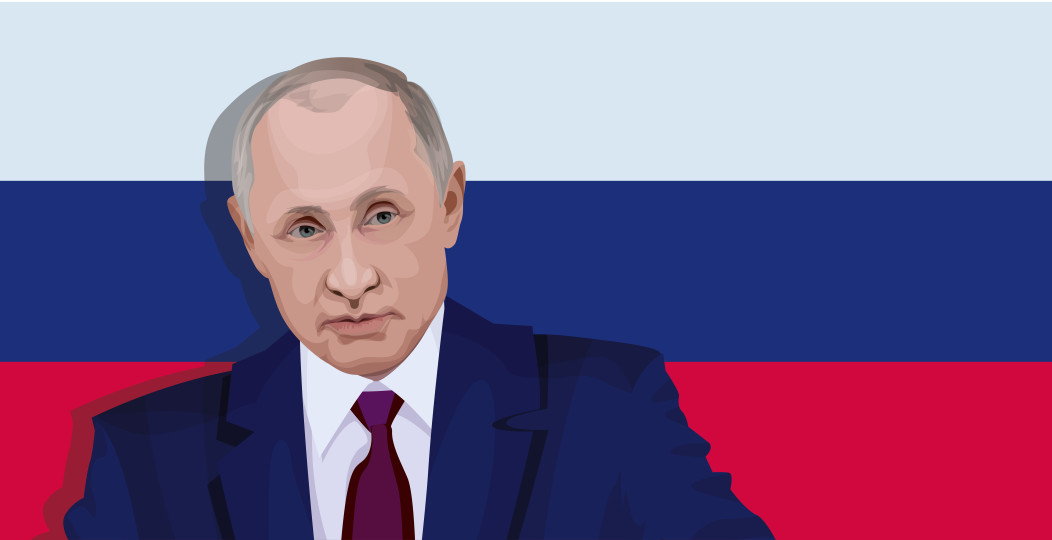
プーチンとロシアの未来
浪費される資源と帝国の野望Subscribers Only 公開論文
プーチンは「特別軍事作戦」を開始するにあたって、ポスト・ソビエトの民主的遺産も否定した。民主的制度の確立に始まり、検閲の廃止、ロシア文化とヨーロッパ文化の再統合にいたるまで、プーチンは、1985年以降にロシアが成し遂げた成果のすべてを、一気にテーブルから振り落とした。その後、短期間で、残された民主的制度を粉砕し、ソビエト期に匹敵する抑圧・監視体制を再確立した。それは1945年以降に出現し、1989年以降に支配的となった世界秩序との決別を意味した。ここからロシアはどこへ向かうのか。侵略というウクライナでの彼の高価なプロジェクトは、実際には、ロシアの経済的、人口的未来に地雷をしかけたようなものだ。
-
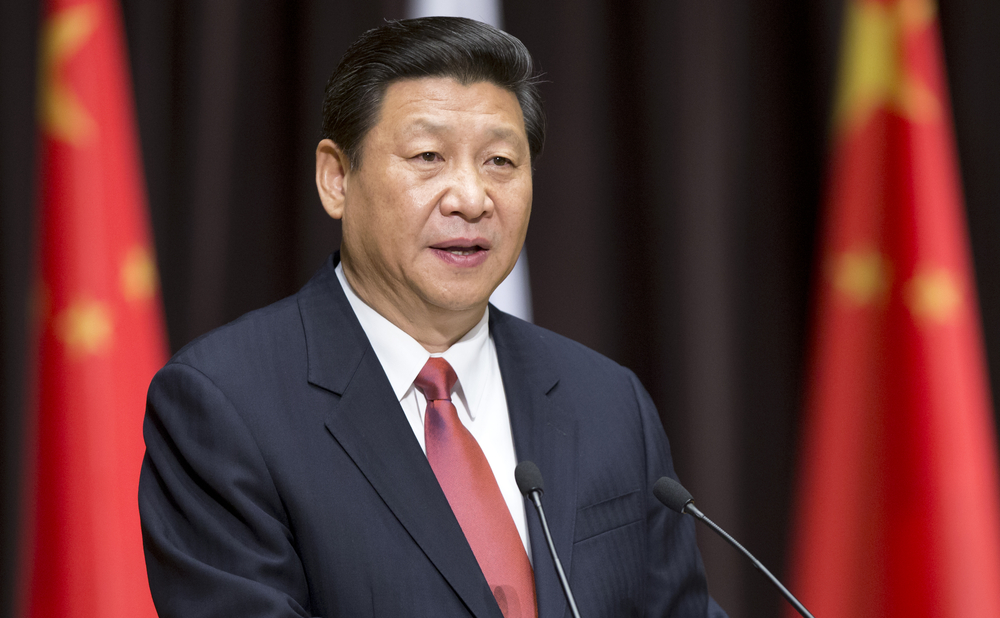
「中国の台頭」の終わり
投資主導型モデルの崩壊と中国の未来Subscribers Only 公開論文
いまや中国はリセッションに直面し、中国共産党の幹部たちはパニックに陥っている。今後、この厄介な経済トレンドは労働人口の減少と高齢化によってさらに悪化していく。しかも、中国は投資主導型経済モデルから消費主導型モデルへの移行を試みている。中国の台頭が終わらないように手を打つべきタイミングで、そうした経済モデルの戦略的移行がスムーズに進むはずはない。でたらめな投資が債務を膨らませているだけでなく、財政出動の効果さえも低下させている。近い将来に中国共産党は政治的正統性の危機に直面し、この流れは、経済的台頭の終わりによって間違いなく加速する。抗議行動、ストライキ、暴動などの大衆騒乱の発生件数はすでに2000年代に3倍に増え、その後も増え続けている。経済の現実を理解しているとは思えない習近平や軍高官たちも、いずれ、中国経済が大きく不安定化し、その台頭が終わりつつあるという現実に向き合わざるを得なくなる。・・・
人口と地政学
-

東アジアの少子高齢化と地政学
世界政治はどう変化するか雑誌掲載論文
東アジアのポテンシャルは、今後、人口減少によって大きく抑え込まれていくだろう。経済成長を実現することも、社会的セーフティーネットを財政的に支え、軍隊を動員することも難しくなり、日本、韓国、台湾は内向きになっていくはずだ。中国も、野心と能力の間の克服しがたいギャップの拡大に直面すると考えられる。一方で、高齢化も進む。中国に悪影響を与える東アジアの人口減少が、ワシントンの地政学的利益になるのは間違いないが、東アジアの民主主義国家にも足かせを作り出し、問題も引き起こす。これらの国家にとって、アメリカとのパートナーシップの必要性が高まる一方で、ワシントンにとって彼らは魅力的なパートナーではなくなっていくだろう。
-

人口動態と未来の地政学
同盟国の衰退と新パートナーの模索Subscribers Only 公開論文
大国への台頭を遂げたものの、深刻な人口動態問題を抱え込みつつある中国、人口動態上の優位をもちながらも、さまざまな問題に足をとられるアメリカ。そして、人口動態上の大きな衰退途上にある日本とヨーロッパ。ここからどのような地政学の未来が導き出されるだろうか。ヨーロッパと日本の出生率は人口置換水準を下回り、生産年齢人口はかなり前から減少し始めている。ヨーロッパと東アジアにおけるアメリカの同盟国は今後数十年で自国の防衛コストを負担する意思も能力も失っていくだろう。一方、その多くがアメリカの同盟国やパートナーになるポテンシャルとポジティブな人口トレンドをもつインドネシア、フィリピン、そしてインドが台頭しつつある。国際秩序の未来が、若く、成長する途上世界における民主国家の立場に左右されることを認識し、ワシントンはグローバル戦略を見直す必要がある。・・・
-

人口減少と資本主義の終焉
われわれの未来をどうとらえるかSubscribers Only 公開論文
ゼロ成長やマイナス成長の社会ではいかなる資本主義システムも機能しない。その具体例が、高齢化し、人口が減少している日本だ。人口の成長がゼロかマイナスの世界では、おそらく経済成長もゼロかマイナスになる。人口規模の小さな高齢社会では消費レベルも低下するからだ。既存の金融・経済システムが覆されることを別にすれば、これに関して、本質的な問題はない。今後、人口比でみれば、十分な食糧が供給され、潤沢に商品が出回るようになるかもしれない。気候変動への余波も緩和されるだろう。だが、資本主義はうまくいってもぼろぼろになり、悪くすると、完全に破綻するかもしれない。今後、世界の人口が減少してゆけば、経済成長は起きるだろうか。この設問にどう応えるかの準備ができていないだけでなく、どう答えるかさえ考え始めていない。これが世界の現実だ。
-

依存人口比率と経済成長
流れは中国からインド、アフリカへSubscribers Only 公開論文
「人口の配当」として知られる現象は経済に大きな影響を与える。この現象は合計特殊出生率が低下し、その後、女性が労働力に参加して人口に占める労働力の規模が拡大し(依存人口比率が低下することで)、経済成長が刺激されることを言う。本質的に、人口の配当が生じるのは、生産年齢人口が増大する一方で、依存人口比率が減少したときだ。実際、出生率の低下と労働力規模の拡大、そして依存人口比率の減少というトレンドが重なり合ったことで、1983年から2007年までのアメリカの経済ブーム、そして中国の経済ブームの多くを説明できる。問題は、先進国だけでなく、これまでグローバル経済を牽引してきた中国における人口動態上の追い風が、逆風へと変わりつつあることだ。人口動態トレンドからみれば、今後におけるグローバル経済のエンジンの役目を果たすのはインド、そしてサハラ砂漠以南のアフリカになるだろう。
-

生産年齢人口の減少と経済の停滞
グローバル経済の低成長化は避けられないSubscribers Only 公開論文
労働人口、特に15―64歳の生産年齢人口の増加ペースが世界的に鈍化していることは否定しようのない事実だ。生産年齢人口の伸びが年2%を下回ると、その国で10年以上にわたって高度成長が起きる可能性は低くなる。生産年齢人口の減少というトレンドで、なぜ金融危機後の景気回復がスムーズに進まないか、そのかなりの部分を説明できる。出生率を上げたり、労働人口に加わる成人を増やしたりするため、各国政府はさまざまな優遇策をとれるし、実際多くの国がそうしている。しかしそれらが中途半端な施策であるために、労働人口の増大を抑え込む大きなトレンドを、ごく部分的にしか相殺できていない。結局世界は、経済成長が鈍化し、高度成長を遂げる国が少ない未来の到来を覚悟する必要がある。
-

赤字と債務にいかに向き合うか
第3の道は存在するSubscribers Only 公開論文
財政赤字と政府債務残高の増大はどの程度深刻な問題なのか。赤字と債務を懸念する原理派は、これらを最大の脅威とみなし、その削減を最優先課題に据えるべきだと主張する。一方、許容派はこれを無視してもかまわないと考えている。実際、政治家が目を向けるべきは、急を要する社会問題であり、財政赤字や債務ではないだろう。財政赤字の削減ではなく、重要な投資に焦点を合わせ、「経済にダメージを与えないように」配慮しなければならない。だが、財政赤字の削減を最優先にする必要はない。高い債務レベルに派生するリスクは、財政赤字削減策が引き起こすダメージに比べれば小さい。このアプローチなら、債務拡大の弊害と財政赤字削減の余波の間の合理的なバランスをとれるはずだ。
-

日本を抑え込む「シルバー民主主義」
日本が変われない本当の理由Subscribers Only 公開論文
日本社会は急速に高齢化している。そして高齢者たちには、政治家が現行の社会保障システムに手をつけるのを認めるつもりはない。だが、高齢社会に派生する問題に向き合うのを先送りすればするほど、その経済コストは大きくなる。これが日本の現実だ。事実、政府の年金財源は2032―2038年の間に枯渇するという試算もある。だが、年齢層からみた多数派で、投票率も高い高齢者集団にアピールするようなキャンペーンを実施すれば、政治家はもっとも忠誠度の高い支持基盤を手に入れることができる。こうして、高齢社会が日本経済にどのようなコストを与えることになるとしても、「高齢者に優しい政策」が最優先とされている。高齢層の有権者の支持を失うことに対する恐怖が、政治家が長期的に国の未来を考えることを妨げ、これが若者に対する重荷をさらに大きくしている。1票の格差同様に、世代間の不均衡問題に目を向け、もっと若者の意見を政治に反映させる必要がある。そうしない限り、日本の経済未来は今後も暗いままだろう。
-

崩壊する「日本というシステム」
Subscribers Only 公開論文
いまや日本人は、日本のシステムからの「退出」路線を選ぶほうが、政府の政策を変えようと試みるよりも好ましいと確信しているようだ。運命共同体的な日本企業も二分され、競争力のある企業は自分だけのボートを保有するようになり、その結果、競争力のない企業が救済措置を求めて日本政府へ影響力を行使することにも異を唱えなくなった。日本の銀行や政府が、形ばかりの再建案と引き換えに、いまも債務まみれのゾンビ企業への新規融資や公共事業を提供するなか、競争力のある日本企業、老後を心配する市民、若い女性たちはこれまでの日本のシステムから退出しつつある。
-
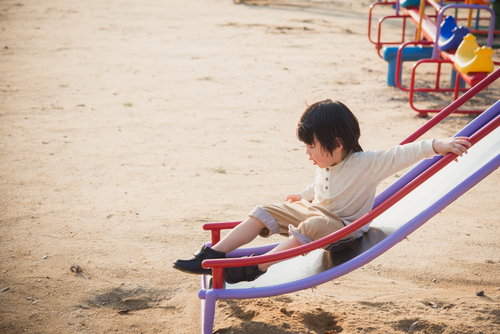
ベビー・ギャップ
出生率を向上させる方法はあるのかSubscribers Only 公開論文
少子化によって課税できる労働人口が少なくなるにつれて、政府は困難な決定を下さざるを得なくなる。社会保障手当を切り捨てて引退年齢を引き上げるか、税率を大きく引き上げるしかなくなるからだ。さらに厄介なのは、労働人口が高齢化していくにつれて、経済成長を実現するのが難しくなっていくことだ。・・・低い出生率は、先進世界の福祉国家体制だけでなく、国の存続そのものを脅かすことになる・・・男女間の差別解消に真剣に取り組まず、女性のための適切な社会サービスの提供に熱心でなかったイタリアや日本のような国は出生率を上昇させられずにいる。これに対して、GDP(国内総生産)の約4%程度を、子育ての支援プログラムにあてているフランスやスウェーデンは出生率の低下を覆すことに何とか成功している。出産奨励プログラムには大きなコストがかかるし、伝統的な家族の価値を支持する人々の怒りを買う恐れもある。だが、低出生率の罠にはまってしまえば、これまでとは不気味なまでに異なる人口減少という未知の時代へと足を踏み入れることになる。
-

少子高齢社会と移民
問題は移民がいなくなることだSubscribers Only 公開論文
「移民危機」という表現が日常的に使われ、反移民感情の高まりを理由に国境を閉ざす国も多い。しかし、先進国の多くでは少子高齢化が進み、高齢者人口が大きくなる一方で、生産年齢人口が小さくなっている。残念ながら、ロボットや人工知能が、人口減少が引き起こす経済的帰結から先進国を救ってくれるわけでもない。こうなると少子高齢化危機への解決策は一つしかない。国境を移民に開放することだ。問題は、移民が先進国に殺到するのではなく、今後、誰もやってこなくなる事態を警戒しなければならないことだ。これが本当の移民危機だ。一人当たり(購買力平価)GDPが7500ドルに達するまでは、途上国の多くの人が外国で働こうと移住を考えるが、国内経済がこのレベルを超えると、パターンは逆転する。
-
Review Essay
移民を受け入れるべきか規制すべきか
移民と経済と財政Subscribers Only 公開論文
移民は基本的に社会モデルが機能しなくなった国から逃れてくる。この事実を踏まえて、その影響をよく考えるべきで、「移民を無制限に受け入れれば、ある時点で受入国と移民出身国の双方にマイナスの影響が出るようになる」と考える研究者もいる。一方、労働市場を移民に開放すると、労働力の供給が拡大するだけでなく、投下資本利益率が上昇して経済成長を加速し、労働需要が高まり、移民だけでなく受入国の住民の生活水準も改善すると考える研究者もいる。実際、移民が受入国の財政にプラスの影響をもたらすことを示す研究は数多くある。経済協力開発機構(OECD)が2013年に27カ国を対象に実施した調査によると、移民が受入国の国庫にもたらす金額は、彼らが受け取る社会保障給付よりも一世帯当たり平均4400ドルも多い。問題は、移民論争がとかく感情的で十分な裏付けが示されないまま、過熱してしまうことだ。
-

イギリスと世界
労働党の世界へのアプローチ雑誌掲載論文
英経済は低成長の泥沼にはまりこんでいる。陸軍の兵力規模は、ナポレオンと戦った時代以来の低水準だし、行政サービスの多くも崩壊寸前だ。保守党政権は、その後の明確な計画もないままに、欧州連合(EU)を強引に離脱し、北アイルランドに平和をもたらした「グッドフライデー合意」を危険にさらし、欧州人権条約を軽視する行動みせた。だが、次の選挙で、われわれ労働党が政権を手に入れば、国家再生の時代を「進歩主義的リアリズム」で切り開いていく。進歩主義を現実主義的に実施すれば、世界を変えられるだろう。進歩主義的リアリズムとは、何が達成できるかに関する誤った思い込みを排除した上で、理想を模索することを意味する。
中東アップデート
-

アラブストリートの反乱
民衆の怒りが米外交を揺るがす雑誌掲載論文
「ガザへの爆撃がついに終わり、人々が家に帰れば、怒りの矛先は違う何かに向けられ、中東の地域政治は平常に復帰する」。ワシントンではこう考えられている。しかし、この仮説は、中東で世論がいかに重要になっているか、2011年の「アラブの春」の騒乱以降、何が本当に変わったのかを理解していない。アラブ民衆の怒りのタイプと激しさ、アメリカの優位の低下と正統性の崩壊、アラブ諸国の政権が地域間競争だけでなく国内体制の存続を優先していることから考えても、新しい地域秩序ではアラブの世論がより重視され、配慮されるようになるだろう。ワシントンがアラブの世論を今後も無視し続けるようなら、ガザ戦争後の計画を台無しにすることになる。
-

イスラエルの次なる戦線?
レバノンをめぐるイラン、ヒズボラとの戦争雑誌掲載論文
ガザの破壊が中東民衆のイスラエルに対する反発を高めるなか、イスラエルがレバノン攻撃すれば、イランとその非国家的パートナー(武装集団)への民衆の支持はさらに強化されるだろう。それでも、政治的に負いこまれたネタニヤフ首相は、国内での立場を強化しようと、レバノンに紛争を拡大するかもしれない。実際、イスラエルは、ハマスとヒズボラをともに壊滅させることで、安全保障環境を変化させることを望んでいる。これまでのところ、アメリカの外交圧力もあって、ガザ紛争がレバノンとの全面戦争に拡大するのは回避されているが、それでも「イスラエルがレバノンを攻撃するかどうか」ではなく、「いつ攻撃するか」が問われている状況にある。
-

中東に忍び寄るドラッグの脅威
カプタゴンからメタンフェタミンへ雑誌掲載論文
カプタゴン(フェネチリン)が中東にまん延している。いまや、シリアが世界のカプタゴンのほとんどを生産し、これが、ダマスカスの重要な収入源とされている。内戦によって無政府状態に陥ったシリアで、イスラム国勢力やヌスラ戦線などのテロ集団が資金集めのためにカプタゴンを生産するようになった。最終的に、これらのイスラム過激派グループをアサド政権は粉砕したが、それは、シリア政府が薬物生産の主導権を握ったことを意味した。アラブ諸国は、カプタゴンのまん延を食い止めるためにアサド政権との交渉を試みてきたが、これまでのところ、シリアが生産量を減少させた証拠はない。それどころか、中東は、カプタゴンよりも作用の強いメタンフェタミンまん延の脅威にいまやさらされつつある。
-

イスラエルの自滅を回避するには
紛争管理からパレスチナとの共存へSubscribers Only 公開論文
ネタニヤフが示した司法改革法案によって、ガザ戦争前の段階で、イスラエル国家は分裂しかねない状況に追い込まれていた。戦争が終われば、この国内状況が再び出現するだろう。パレスチナをめぐっては、ネタニヤフのように「パレスチナを永遠に占領できる」と考えるのか、それとも「共存が必要」とみなすかが、今後問われることになる。「紛争管理」と「草刈り」が今後もパレスチナ問題に対処する政策であるなら、占領、入植政策、強制退去がさらに続く。しかし、このやり方は、さらなる大惨事を招き入れるだけだ。安心して生活し、尊重し合える共存を望むのなら、イスラエルはパレスチナ人に手を差し伸べ、ともに協力していかなければならない。
-

イスラエルはどこに向かうのか
ネタニヤフとの決別をSubscribers Only 公開論文
ガザの戦後をめぐって、ネタニヤフがワシントンの計画を受け入れれば、極右の連立パートナーの支持を失い、政権は崩壊するだろう。一方、バイデンの計画を拒否し続ければ、ガザの泥沼に深く引きずり込まれる。この場合、西岸で第3次インティファーダが誘発され、イランが支援するレバノンのヒズボラと再び戦争に突入するだろう。しかも、アメリカとの関係が大きく損なわれる危険がある「アブラハム合意」も不安定化し、サウジアラビアがこの合意に参加することへの期待も遠のく。ネタニヤフがイスラエルを長い地域戦争へ導き、おそらく米政権とイスラエル市民を欺くのを防ぐには、総選挙を実施するしかない。われわれはどこに向かっているのか、誰がわれわれをそこに導くのかを市民が決められるようにする必要がある。・・・
-

イランの戦略目的は何か
混乱と変動から利益を引き出せる理由Subscribers Only 公開論文
テヘランは混乱のなかにチャンスをみいだしている。イランの指導者たちは、ガザ戦争を利用し、エスカレートさせることで、イスラエルを弱体化させてその正統性を失墜させ、アメリカの利益を損ない、地域秩序を自国に有利なものへ変化させようとしている。混沌とした状況から自国の利益を導き出すイランの能力を侮るべきではない。攻撃によってアメリカを刺激し、テヘランとその同盟国が有利になるようなミスを犯させたいとテヘランは考えている。だが、イランを含む関係勢力のいずれかが誤算を犯せば、中東全域でより激しい紛争が発生し、中東の安定とグローバル経済に大きなダメージが生じる恐れがある。
-

中央アジアを揺るがすタリバーンの正体
Subscribers Only 公開論文
アフガニスタンの平和の実現を助けずして、中央アジアの広大な石油・天然ガス資源を安全に開発できると考えるのは、非現実的である。タリバーンが牛耳るアフガニスタンは、今やパキスタン、イラン、中央アジア諸国、イスラム教徒の多い中国の新疆ウイグル自治区の反政府イスラム勢力が安心して逃げ込める「聖域」となっているだけでなく、軍事訓練の拠点と化している。実際、タリバーンと協力して現在アフガニスタンで戦っている数千のイスラム原理主義者たちは、いつか祖国の政権を倒し、世界各地でタリバーン流イスラム革命を起こすつもりなのだ。しかも、アフガニスタンは今や世界最大のアヘン生産国で、この犯罪経済に周辺諸国が巻き込まれつつある。タリバーンが支配するアフガニスタンから、暴力、麻薬、カオス、テロリズムが周辺地域へと拡散するのを放置すれば、いずれわれわれは途方もないコストを支払わされることになる。







