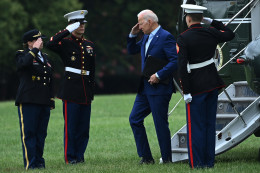台湾防衛の強化に向けて
―― 中国の侵略を防ぐためにアメリカがすべきこと
2022年3月号

アメリカは台湾をめぐる戦争で敗北する軌道にある。だが今からでも路線を見直せる。既存のすぐに手に入る軍事資源の分配を見直し、より効率的な計画を立て、重要な同盟関係をうまく生かせば、アメリカは早ければ2020年代の半ばまでには、台湾をめぐる戦争を阻止し、必要であれば相手に勝利する能力を手に入れているはずだ。中国共産党の自制心や10年以上先にならなければ利用できない技術に賭けるのではなく、アメリカの議会と政府は、新たな太平洋防衛戦略を遂行しなければならない。「バトルフォース2025」を新たに構築すれば、アメリカとその同盟国は、中国の侵攻を短期的に抑止し、必要に応じて撃退できるようになる。