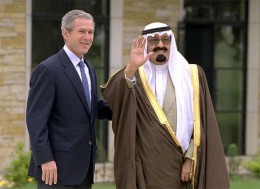米外交問題評議会リポート
イラクに侵攻すれば、世界はどう反応する
2002年12月号

アラブ世界では、アメリカがイラクを粉砕したいのは、イラクが中東地域でのイスラエルの覇権確立を阻む唯一の力を持つ国だからだ、という考えも流布している。民主主義を相手に押しつけることはできない。だが、人権を尊重するような政権をイラクに樹立するというのならまだ話はわかる。ジェファーソン流の民主主義者を中東に見いだそうとしても無理だが、政府の説明責任、透明性、市民の政治参加、マイノリティーの尊重、女性の権利の確立などの基本的価値をアメリカと共有している人材なら見いだせる。(ヒシャム・メルヘム)