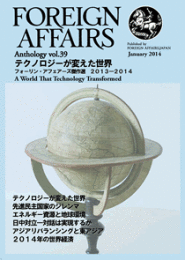依然として重要なサウジ石油
―― 米シェール資源はライバルではない
2014年2月号

アメリカのシェール資源ブームは世界最大の産油国サウジアラビアにとって厄介な事態だと考える人もいる。だがこれは、リヤドにとってもグッドニュースなのだ。市場の先行き不透明感をひどく嫌がるリヤドにとって、シェール資源を含む多様なエネルギー生産が進めば、市場の不透明感と急激な変動を抑えることにつながるからだ。さらに、いかなる国もサウジのような大規模な余剰生産能力を提供できない以上、これまでサウジに多くを依存してきた石油市場の構図は今後も変化しないだろう。むしろ、サウジにとって厄介なのはイラク、イラン、リビアが今後石油供給を増大させていくと考えられることだ。この場合、原油価格の下落を阻むために、サウジが減産を求められる可能性もある。サウジ国内の石油消費が増えていることも問題だ。2020年代末までには、サウジの国内消費量が輸出量を上回るようになると考えられる。・・・