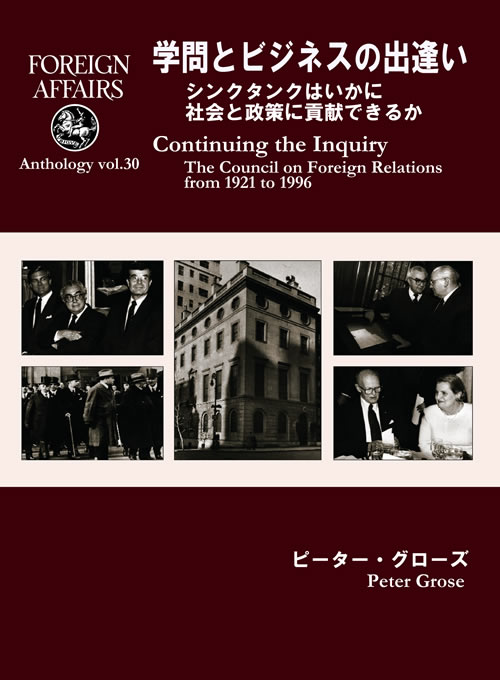
Vol.30 学問とビジネスの出逢い
――シンクタンクはいかに社会と政策に貢献できるか
/ ピーター・グローズ
Continuing the Inquiry
The Council on Foreign Relations from 1921 to 1996
掲載論文
ベルサイユ講和会議に参加したアメリカの学者チームは、帰国後、アメリカに国際問題研究所を立ち上げようと試みる。だが、彼らは、外交経験を語り、外国の指導者との接触を実現することはできても、なにせ資金を欠いていた。一方、法曹界、銀行界のメンバーたちは、学問的な知性、ダイナミズム、そして外国の指導者との接触を必要としていた。このビジネスと学問の必要性の出逢いこそが、現在の外交問題評議会の成長を促し、その後何十年にもわたってこの組織を傑出した存在とした「シナジー」、つまり、共働作用を生み出した。学問的、政治的専門意見が、現実的なビジネス利益と出逢い、このプロセスによって、概念的思索家たちが、「岩の上にたっているのか、あるいは、流砂の上にたっているのか」を見極める機会が提供されることになる。
- 第一章 ベルサイユ条約と外交問題評議会の誕生
- 「インクワイアリー」の精神
- 象牙の塔から外交の場へ
- ビジネスと学問の出会い
- 外交問題評議会(カウンシル)の誕生
- 第二章 基本的な前提
- 公開と非公開のバランス
- 良識ある大衆と『フォーリン・アフェアーズ』の誕生
- 第三章 多様性をめぐる対立
- メンバーの拡大と評議会のジレンマ
- 「外交問題委員会」の設立
- ヨーロッパ志向の克服
- 忍び寄る井戦争の足音
- 第四章 「戦争と平和の研究」プログラム
- 国務省とカウンシル
- 政策決定に果たした役割
- 第五章 最初の変革
- ハロルド・プラット・ハウス
- 対ソ協調路線の模索
- 幻と消えたフランクリン・レポート
- 第六章 冷戦と「X」論文
- ケナンと『フォーリン・アフェアーズ』
- マーシャル・プラン
- インドシナ戦争とアメリカの立場
- キッシンジャーのデビュー
- 中国研究プロジェクトとニクソン訪中
- 第七章 危機にさらされたコンセンサス
- カウンシルから国務省へ
- 大学、郡、政府との交流プログラム
- メンバーの多様化
- ベトナムとカウンシルの亀裂
- 第八章 第二の変革
- 新たな時代と新たな使命
- 組織改革と活動の変化
- 1980年代プロジェクト
- 21世紀に向けて
アメリカの外交政策をめぐる止めどない論争の中から、新規ですばらしいアイディアがでるのはきわめて希なことであり、また、言論を鍛え合う場がなければ、そのアイディアですら、日の目を見ることはない。1921年以来、外交問題評議会は、栄誉ある有力な非政府組織として、アメリカが国際社会でいかなる立場をとるかを論じる壮大な舞台の監督の役割を果たしてきた。
今日まで75年にわたって、外交問題評議会(カウンシル)のメンバーは、メンバー同士でもまた外部の人間に対しても、自説を語りまた他人の意見に耳を傾け、その過程において、さまざまな洞察や明晰な考えを具体的な政策に結実させるという栄誉を担ってきた。またそのような希ですばらしい瞬間に出会えぬ場合には、当代最高の議論に耳を傾け、それに加わることで満足しなければならなかった。
本書において、ピーター・グローズは玉石混淆のカウンシルの史実を描き出している。われわれがピーターにカウンシルの歴史に取り組むことを依頼したのは、彼がメンバーとして、上級研究員として、さらには、われわれが誇る「フォーリン・アフェアーズ」誌の元副編集長としてこの組織を熟知しているだけでなく、著名かつ誠実なジャーナリストであり、また歴史家だからである。本書における記述や見解は、全て彼自身のものであり、われわれは事実に関する正確さを期す以外の要請はしていない。
読者の中には、この公正な歴史の中で浮かび上がるカウンシルが、巷で言われているほど陰謀をめぐらす存在でも、世界を裏で操る伏魔殿でもないことを知りがっかりする人がいるかもしれない。グローズの書く物語は、議論というものは、そもそも同質的な背景をもつ人物たちが、結局はそう多くについて同意できないことを見いだすことになる画期的なディナー・ミーティングの時代へとさかのぼるが、メンバーたちの多様性が増したここ20年間をみても、葉巻の煙でやすらぐことができなくなった以外は、環境は変わっていない。
カウンシルについて昔も今も特記されるべきは、ハロルド・プラット・ハウスの内側のメンバーたちがみなきわめて冷静だということだ。カウンシルの会議や「フォーリン・アフェアーズ」の議論・論争には、むき出しの敵意や党派的色彩などみられない。この価値ある節度に加えて、メンバーたちがみな、アメリカ人は世界を知る必要があり、そのうえで国際情勢に関して主導的役割をはたさねばならないと確信していたことが、カウンシルを特別な存在にしたのだ。
この75年にわたって、組織体としてのカウンシルが何かを具現してきたとすれば、それは常にアメリカの利益に基づく国際主義だったといえよう。もしこれまでカウンシルが何らかの影響力を持ったとすれば、それはさまざまのそしてしばしば紛糾する一連の会議を主催し、広く米市民に向けてさまざまな出版物を送り出した個々のメンバーの力によるものだった。「フォーリン・アフェアーズ」に掲載されたW・E・B・デュボイスやジョージ・F・ケナンの論文からヘンリー・キッシンジャーやスタンレー・ホフマンの著作にいたるまで、今も昔もカウンシルの役割といえば、最善の知性と指導者を見つけだし、カウンシルの他のメンバーと接触させ、研鑽と討論の舞台を提供することにある。
ピーター・グローズは、この点を十分に論じている。カウンシルの理事長、ピーター・ピーターソン、(カウンシルの歴史の約3分の1の間われわれの組織のために尽力してきた)上席副会長のオルトン・フライ、そして私は、グローズの労作を一読されることを、自信をもって薦めるものである。
レスリー・ゲルブ/外交問題評議会会長
(肩書きは執筆当時のもの)
この論文はSubscribers’ Onlyです。
フォーリン・アフェアーズリポート定期購読会員の方のみご覧いただけます。
会員の方は上記からログインしてください。 まだ会員でない方および購読期間が切れて3ヶ月以上経った方はこちらから購読をお申込みください。会員の方で購読期間が切れている方はこちらからご更新をお願いいたします。
なお、Subscribers' Onlyの論文は、クレジットカード決済後にご覧いただけます。リアルタイムでパスワードが発行されますので、論文データベースを直ちに閲覧いただけます。また、同一のアカウントで同時に複数の端末で閲覧することはできません。別の端末からログインがあった場合は、先にログインしていた端末では自動的にログアウトされます。
(C) Copyright 1996, 2008 by the Council on Foreign Relations, Inc., and Foreign Affairs, Japan


