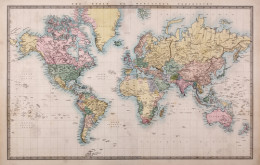ハイチの悲惨な現実
2011年2月号

2010年1月に大地震に見舞われたハイチの復旧・再建活動はうまく進展していない。地震で家をなくした人は、いまもそのままだし、ほとんどの政府施設やインフラも依然として再建されていない。しかも、2010年10月にはコレラが発生して猛威を振るいだし、いまも感染を広げ、犠牲者が増えている。クリスマス以降、犠牲者数は1日平均100人に達し、2011年1月1日までの犠牲者総数は3651人に達している。最大の問題は清潔な飲料水を提供するインフラが存在しないことだ。いまや水田に入ればコレラに感染するのではないかと恐れて、農家が稲を水田に植えることさえ嫌がるようになった。ハイチが必要としているのはインフラと統治だが、それが短期的に満たされる可能性は低い。