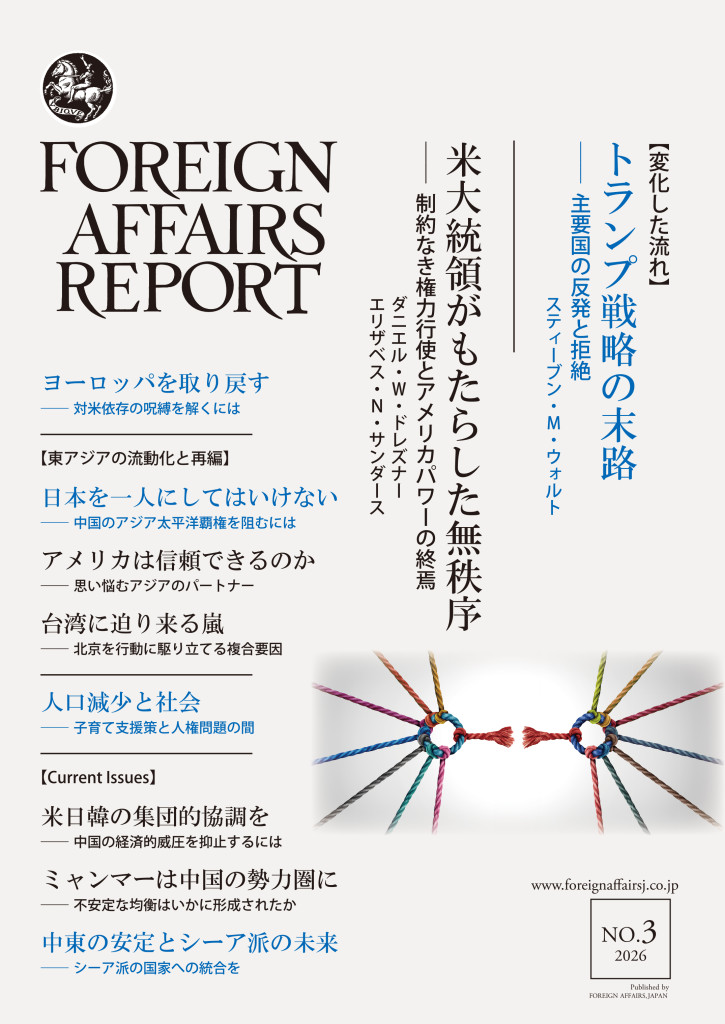Kaua209 / Shutterstock.com
2026.2.27 Fri
トランプにどう向き合うか
―― ヨーロッパとアジア
アメリカパワーの基盤は、国内での法の支配と国外における信頼できるコミットメントで形作られているが、トランプは、まさにこれを解体しようとしている。アメリカから距離を置くようになった同盟国は、不安定なアメリカに対する保険策として中国そして他の同盟諸国への接近を試み始めている。(ドレズナー、サンダース)
ドナルド・トランプの任期が終われば、米欧間の悪夢も魔法のように消えてなくなると期待するのではなく、欧州連合(EU)は、アメリカに屈服するのをやめて、より大きな主権を構築する必要がある。目標は、ヨーロッパの運命はヨーロッパが握っているという感覚を取り戻すことだ。(マティス、トッチ)
日米は重要な岐路に立たされている。東京が、中国との長期にわたる対立に備えて大胆な措置をとり続けるなか、ワシントンのコミットメントは揺らいでいる。東京は難しい部分をこなしてみせた。今度はワシントンが立場を強化しなければならない。(ブルメンタール、クイケン、シュライバー)
米大統領がもたらした無秩序
―― 制約なき権力とアメリカパワーの終焉
2026年3月号 ダニエル・W・ドレズナー タフツ大学フレッチャースクール 特別教授(国際政治学) エリザベス・N・サンダース コロンビア大学政治学教授

いまや米大統領は国の内外で、制約などほとんど気にかけることなく、思うままに行動している。米市民も、トランプが世界に解き放ったのと同じ「ホッブズ的な無秩序」のなかに置かれている。行動へのあらゆる制約を拒み、技術によって旋風のように動けるようになったことで、より大胆になった指導者が作り出すホッブズ的秩序では、「何でもあり」だ。アメリカパワーの基盤は、国内での法の支配と国外における信頼できるコミットメントで形作られているが、トランプは、まさにこれを解体しようとしている。アメリカから距離を置くようになった同盟国は、不安定なアメリカに対する保険策として中国そして他の同盟諸国への接近を試み始めている。
ヨーロッパを取り戻す
―― 対米依存の呪縛を解くには
2026年3月号 マティアス・マティス ジョンズ・ホプキンス大学 高等国際学院准教授 ナタリー・トッチ ジョンズ・ホプキンス大学 高等国際学院ボローニャ校教授

ドナルド・トランプの任期が終われば、米欧間の悪夢も魔法のように消えてなくなると期待するのではなく、欧州連合(EU)は、アメリカに屈服するのをやめて、より大きな主権を構築する必要がある。目標は、ヨーロッパの運命はヨーロッパが握っているという感覚を取り戻すことだ。戦略的自律性を確保することは、必ずしも、ワシントンとの対立や米欧同盟の放棄を意味しない。重要なのは、必要なときは「ノー」と言い、利害が一致しないときは独自に行動し、ヨーロッパ内で一貫性のあるプロジェクトを維持する能力をもつことだ。
日本を一人にしてはいけない
―― 中国のアジア太平洋覇権を阻むには
2026年3月号 ダン・ブルメンタール アメリカン・エンタープライズ研究所 シニアフェロー マイク・クイケン スタンフォード大学フーバー研究所 特別客員研究員 ランドール・シュライバー 元米国防次官補

日米は重要な岐路に立たされている。東京が、中国との長期にわたる対立に備えて大胆な措置をとり続けるなか、ワシントンのコミットメントは揺らいでいる。東京は難しい部分をこなしてみせた。今度はワシントンが立場を強化しなければならない。中国は、アジア太平洋の覇権を握るという野望を実現する上で、日米同盟が最大の障害であることを理解している。経済的にレジリエントで、外交的に活発で、軍事能力の高い日本なら、台湾を孤立させ、近隣諸国を威圧し、アメリカがこの地域に関与するコストを引き上げる北京の計画を損なうことができる。アメリカは、日本と同盟国にとって台湾有事は存立にかかわるという高市の発言を支持して、同盟国と共にあることを示す必要がある。